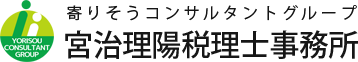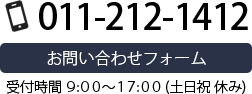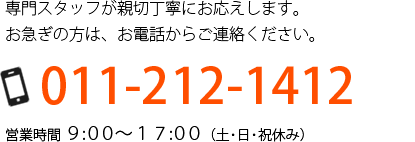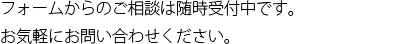もういくつ寝ると…でもないですが、2月14日はバレンタインデーです。 で、バレンタインデーと言えばチョコレート。 チョコレート業界にとっては一大イベントとなりますが、在宅勤務の拡大の影響などで「義理チョコ」は絶滅の危機に
…続きを読む
バレンタインデーに見るマーケティング戦略
2021/02/09
2022講演会、オンライン開催決定!
2021/01/15
カリスマ経営コンサルタント・神田昌典さんの全国縦断公園ツアー「2022」、今年も開催決定です。 ただ何せ緊急事態宣言が発令されたこのご時世、今年は全国縦断しません。完全オンライン形式での講演会となります。 振り返ると、こ
…続きを読む
コロナでスーツが売れないようですが・・・
2020/12/18
コロナにより影響を受けた業界は多々ありますが、ビジネス系ファッション業界も大きな影響を受けているようです。 「洋服の青山」や「THE SUIT COMPANY」などを展開する紳士服大手の青山商事が先日発表した2021年3
…続きを読む
コロナ禍で焼肉店が増えていますが
2020/12/14
コロナ禍の中、最近焼肉店が増えているそうです。 私も過去「ワタミの脱居酒屋戦略に考える」という記事(コチラ)で取り上げましたが、居酒屋チェーン大手のワタミは全国の居酒屋360店舗のうち120店舗をこれから1年半かけて焼肉
…続きを読む
選択と集中は幻想?
2020/12/09
先日『なぜソニーは好調なのか?「選択と集中」という幻想』という毎日新聞社のネットニュースを見つけました。 ソニーはトリニトロンテレビやウォークマンなどの画期的な商品で戦後の高度経済成長を牽引しましたが、バブル崩壊後は他の
…続きを読む
いま勢いのある肉料理店に学ぶ
2020/12/02
11月29日放送の「坂上&指原のつぶれない店」では沖縄県発のステーキ店「やっぱりステーキ」が取り上げられていました。 本格的なステーキがスープ飲み放題、サラダ・ご飯食べ放題もついて1,000円で楽しめるというコスパの良さ
…続きを読む
コロナ禍で電話営業が増えているようですが・・・
2020/11/18
コロナによりアポ無しの訪問営業は激減したそうです。 まぁそうですよね。 これだけコロナの感染対策を徹底しましょう。ソーシャルディスタンシングですよ。と言っているのに、見ず知らずの人にいきなり押しかけられるのは勘弁して欲し
…続きを読む
VUCAの時代に飛躍するには?
2020/11/02
先日、一番化戦略コンサルタント・高田稔先生に札幌にお越しいただき、毎月恒例のグループコンサルを行っていただきました。 当事務所経由でコンサル契約をしていただいている方には毎月グループコンサルに参加いただけるようになってお
…続きを読む
大塚家具の久美子社長退任に思う
2020/10/30
大塚家具の大塚久美子社長が12月1日付けで代表取締役を辞任するという発表がありました。 ”大塚久美子社長が来期の黒字化に向けて道筋がつきつつあることから、過去の業績についての責任を明確にする意味で申し出たという” とのこ
…続きを読む
ヤベェよ、ダブチ戦略
2020/10/28
「ヤベェよ、ダブチ!」 みなさん、ダブチってご存知ですか? これ、マクドナルドの人気メニュー「ダブルチーズバーガー」を縮めたもので、最近キムタクを起用したCMでキャンペーンを展開しています。 マクドナルドのホームページを
…続きを読む