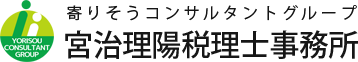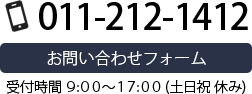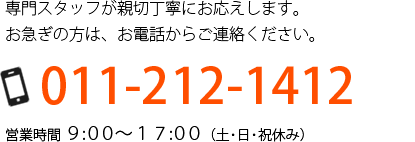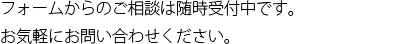2月1日に東京で開催された神田昌典さんの2022講演会に行ってきました! 2月23日には札幌でも開催しますので、そこでもお話を聴けるのですがそれでもわざわざ東京会場に行ったのには訳があります。 その理由はズバリ、「会場が
…続きを読む
神田昌典さんの2022講演会に一足先に行ってきました!
2019/02/04
節分の由来
2019/02/03
本日は「節分の日」ですね。 節分とは「季節を分ける」という意味があり、各季節の始まりの日である立春、立夏、立秋、立冬の前日となります。 ただ江戸時代以降は特に立春の前日を指すようになり、現在に至っています。 立春は毎年固
…続きを読む
日本一危険な神社
2019/02/02
今年の初めに確か「めざましテレビ」で紹介されていたと記憶していますが、「日本で一番危険な神社」が取り上げられていました。 しかもそれはなんとここ北海道に存在するというのです。 その神社の名は「太田神社」。 せたな町という
…続きを読む
2月の戦略マーケティング・ブートキャンプ情報
2019/02/01
つい先日”一番化戦略コンサルタント”高田稔先生による戦略マーケティング・ブートキャンプを開催したばかりですが、2月もやります! 次回は2月27日開催となりますので、詳細は当サイトの「セミナー情報」ページよりご確認願います
…続きを読む
ポスト平成のキャリア戦略
2019/01/31
いよいよ「平成」も今年で終わりますが、最近よく聞くフレーズが「ポスト平成」。 要は「平成のあと」ということですが、実際どんな時代になるのか気になるところですね。 ※いきなり余談ですが「ポスト」には①郵便箱②柱③地位・役職
…続きを読む
一番になることの大切さ
2019/01/30
今月も一番化戦略コンサルタント・高田稔先生をお迎えしてマーケティングセミナーを行いました。 先生の肩書きに「一番化」とありますが、一番を目指すことは非常に重要なことです。 かつて「一番(世界一)になる理由は何があるんでし
…続きを読む
インパクトカンパニー読書会やります!
2019/01/29
度々ご案内していますが2月23日に札幌にて経営コンサルタント・神田昌典さんの講演会「2022」を開催します。 カリスマ・マーケッターにしてトップコンサルタントである神田さんのお話しを札幌で直接聴くことができるまたとない機
…続きを読む
イチ社員がティール変革を起こせるか?
2019/01/28
先日今年最初のティール組織読書会に参加しました。 約500ページのぶ厚い本ではありますが、昨年から少しずつ読み進め400ページを突破しました。 本書は三部構成で第一部は組織モデルの歴史とティール組織の概要について解説され
…続きを読む
大神宮と神宮の関係性
2019/01/27
前回の「神社で行う神前結婚式」を読んだ方からこんな質問をいただきました。 「東京大神宮って”神宮”とついているのに、以前に紹介していた全国に24社ある神宮の中に入っていないのはなぜですか?」 おぉなるほど!いい質問ですね
…続きを読む
神社で行う神前結婚式
2019/01/26
神社で結婚式を挙げるいわゆる「神前結婚式」が増えているそうです。 確かに土日祝日に神社を参拝すると遭遇することも多いですし、おそらく皆さんも同じような経験をしているのではないでしょうか? 実際私の弟も北海道神宮で神前結婚
…続きを読む