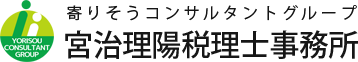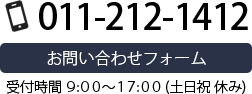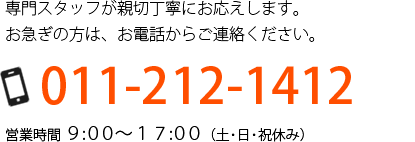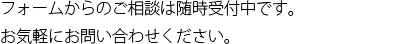前回「ウルトラマン世代」「ポケモン世代」「ドラクエ世代」で盛り上がりすぎて(途中のRPGネタが不要だったという説も)、1回で収まらなかった神田昌典さんの最新刊『インパクトカンパニー』を読んでの学び・気付きポイントの続きと
…続きを読む
インパクトカンパニー②
2019/02/14
インパクトカンパニー
2019/02/13
現在2022講演会で全国を縦断中の神田昌典さんの最新刊『インパクトカンパニー』。 先日神田明神で開催されたプレミアムな回に参加する際に、事前に読んでいきましたが、ぶっちゃけて言います・・・ 「2022講演会に参加する人は
…続きを読む
価格設定の思い込み
2019/02/12
以前のブログで価格設定について言及しました(コチラ)が、その中で ”と言ってる私自身が税理士業界一筋の人間で、「税理士報酬はこんなもの」というパラダイムを持っていますので、自分自身がパラダイムシフトをする必要がありますが
…続きを読む
建国記念の日の由来とは?
2019/02/11
本日2月11日は「建国記念の日」ですが、どんな日かお分かりでしょうか? 「え、建国記念って言ってるんだから日本という国ができた日でしょ?」 では、日本という国ができたというのはいつの時点を指すでしょうか? ・敗戦により”
…続きを読む
2月10日は何の日?
2019/02/10
今日2月10日はみなさんご存知のあの記念日です! そう、「簿記の日」です! ・・・ご存知ない?? まぁ確かに私も知ったのはつい最近ですので、知らなくても仕方のないところでしょう。 こういう記念日には「その日になんらかの由
…続きを読む
神田明神の魅力
2019/02/09
先日神田昌典さんの2022講演会参加のために訪れた神田明神ですが、私の好きな神社の一社です。 そこで今回は神田明神がどんな神社なのかご紹介したいと思います。 まず神田明神は東京都千代田区外神田に鎮座しています。御茶ノ水駅
…続きを読む
神田さんの講演会は1度行けばOK?
2019/02/08
神田昌典さんの2022講演会の札幌開催まで約2週間となりました。 今年に入って順調にお申込みをいただいており、神田さんも参加される予定の懇親会についてはすでに満席という状況です。 札幌人には「ギリギリまで保留して最後の最
…続きを読む
なんで、その価格で売れちゃうの?
2019/02/07
このブログでは過去何度も「価格設定の大切さ」について言及してきました。 医療や福祉の診療報酬など自分で勝手に決められないという例外を除き、基本的に自社の商品・サービスをいくらで販売するかという決定権は自社にあります。 つ
…続きを読む
PayPay始めました!
2019/02/06
先日「100億円キャンペーン」の第2弾を発表したPayPayですが、このタイミングで当事務所もPayPayの取り扱いを開始しました。 と言っても、今回のキャンペーンに合わせた訳ではなく、昨年末に加盟店の申請をしていたのが
…続きを読む
星野リゾート・星野社長に学ぶ原理原則の大切さ
2019/02/05
先月の「がっちりマンデー!!」は「スゴイ社長たちが大集合!!」ということでこんな社長たちが集結していました。 旭酒造株式会社 会長 桜井博志さん 株式会社ニトリホールディングス 代表取締役会長兼CEO 似鳥昭雄さん 日本
…続きを読む