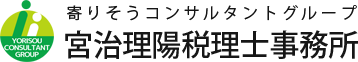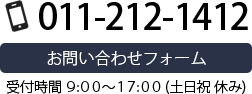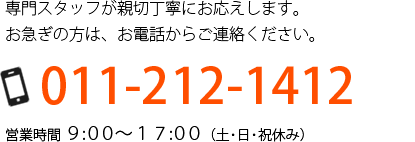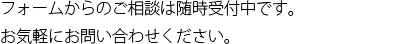前回の記事で『あなたの会社が90日で儲かる!』を取り上げましたが、初版発行日は1999年12月20日。 そして前回の記事を投稿した日が2018年12月20日。 狙ったわけではありませんが、偶然にも発行記念日に取り上げたこ
…続きを読む
神田昌典さんとの出会い②
2018/12/21
神田昌典さんとの出会い①
2018/12/20
当事務所は経営コンサルタント・神田昌典さんが年初に行う全国縦断講演ツアー「2022」の北海道会場の事務局を担わせていただいています。 もともとはイチ参加者だったのが、運営側に回っているというのはなんとも不思議な感覚ですが
…続きを読む
RIZAP式をプチ体験!
2018/12/19
あのRIZAPによる健康経営セミナーに参加しました。 健康経営とは「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」だそうで、やはり税理士・社労士としては押さえておきたいところ・・・なのですが、まぁ今回参加し
…続きを読む
白井一幸さんに学ぶ「組織の成果を120%にする3つの原則」
2018/12/18
12月16日に元北海道日本ハムファイターズコーチ・白井一幸さんをお招きしてJPSA札幌支部特別講演会を開催しました。 日曜日の昼間にも関わらず120名を超える方にご参加いただき、ありがとうございました! 今回白井さんには
…続きを読む
今年の漢字
2018/12/17
毎年恒例の「今年の漢字」。 2018年の漢字は「災」になりましたね。 全国的に台風や地震が多発しましたし、ここ北海道も地震で停電・断水を経験するなど確かに災害の多い1年でした。 と考えると、今年を表わしているとも言えるの
…続きを読む
神宮や大社って何?
2018/12/16
私が神社について本格的に学び始めて疑問に思ったのが、「〇〇神社」「〇〇神宮」「〇〇大社」「〇〇宮」などの違いが何なのか?という点です。 同じように疑問に思っている人もいるのではないでしょうか? ということで、今回はこれら
…続きを読む
ボヘミアン・ラプソディ
2018/12/15
先日、映画『ボヘミアン・ラプソディ』を観に行きました。 言わずと知れた伝説のバンド「QUEEN」、特にボーカルのフレディ・マーキュリーを取り上げた内容で、かなり話題になっていますね。 私は残念ながらリアルタイムではほとん
…続きを読む
8年ぶりのナイストライ!
2018/12/14
11月に東京で受検した「ビジネス選択理論能力検定準1級」の結果が届きました。 結果は・・・不合格でした。 ”不”合格だとネガティブなイメージがあるため、以後「でもよくチャレンジしたよ!頑張ったよ!」という意味で「ナイスト
…続きを読む
わくわく夢を叶えるミニ宝地図づくり体験をしませんか?
2018/12/13
このブログで過去何度も取り上げてきた「宝地図」。 今までは友人知人から「作りたい!」というオファーがあった際にクローズドで宝地図作成セミナーを行ってきました。 「今後はオープンセミナーもやりますので、その際はご案内します
…続きを読む
12月のティール組織読書会開催レポート
2018/12/12
以前にご紹介した『ティール組織』を月イチで集まり、みんなで読もうという趣旨のティール組織読書会ですが、先日年内最後の開催となりました。 500ページ以上もあり、一人だと途中で挫折するかもしれない(文字通り)ぶ厚い壁もみん
…続きを読む